受験でもかなり重要になってくる内申書。
しかし、一体何が書かれていて、どのような行動や結果が内容に影響を与えるのかを知っている方は少ないのではないでしょうか?
今回は内申書について、その定義から内容に影響を与える行動、部活や生徒会活動との関係性について解説していきます。
内申書とは?
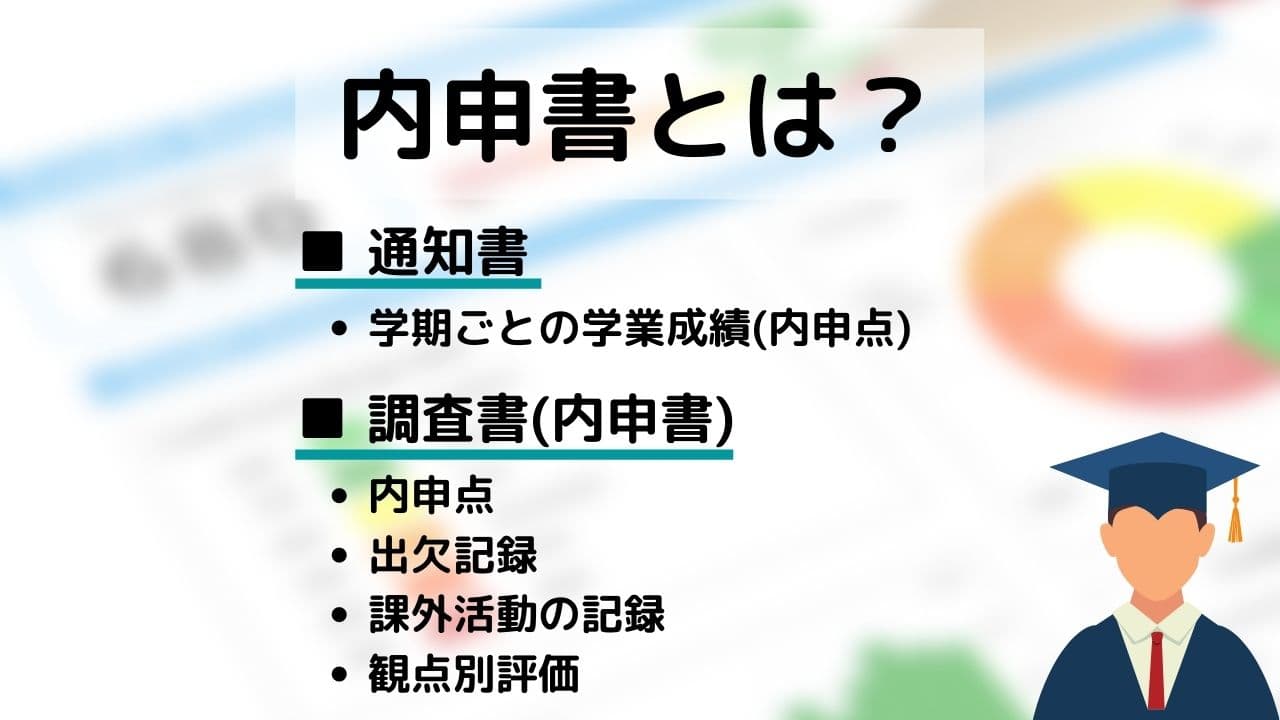
受験において内申書は重要だと知っている方は多いです。
しかし、内申書に何が書かれていてどのような行動が影響を与えるのかについて説明できる方は少ないのではないでしょうか?
ここでは、そもそも内申書とはなにか、何が書かれているのかについて解説してきます。
通知表、評定
まず、内申書とは別に通知書というものがあります。
通知表には学期ごとの学業成績が記載されています。
また、教科別・観点別の五段階評価に加え、担任の先生からの文章による所見が載っていることもあります。
中学一二年生の時点で受験する高校が決まっていない場合は、通知表の結果を重く受け止めるより、教科の得意不得意を知るための指標にするのが良いでしょう。
苦手な教科は家庭教師を頼むなどの対策をとることが出来ます。
調査書、調査書点
一般に内申書と呼ばれるものは調査書と言います。
調査書には先ほどの学業成績に加え、課外活動や出欠記録などが載っています。
調査書は受験する高校に送られ、合否を判断する材料の一つとして扱われます。
つまり、その受験生がどのような中学校生活を送ったかを受験する高校に示すためのものと言うことが出来ます。
調査書には、各学年の年度末に出た評定が記載されます。
ただし、三年生は年度末の評定が受験に間に合いません。
そのため、三年生のみ2学期制の場合は後期の中間テストまでの評定、3学期制の場合は2学期の評定が記載されます。
ここで注意すべきことがあります。
それは、都道府県によって記載される学年にばらつきがあるということです。
3年生の評定のみの場合や1~3年の評定を記載することもあるので注意しましょう。
観点別評価に加えて、観点別評価を記載する場合もあります。
観点別評価とは、各教科について以下の観点でそれぞれの達成度をABCの3段階で評価したものです。
- 「関心・意欲・態度」:提出鬱、発言など授業態度が前向きか
- 「思考・判断」:学んだことを自らの知識としてアウトプットできているか
- 「技能・表現」:学んだことを適切に使えているか
- 「知識・理解」:正しく理解でいているか
自分の行きたい/お子さんに通わせたい高校の判断基準はどこにあるのかを前もって調べておくことが重要になります。
内申書と高校受験の関係
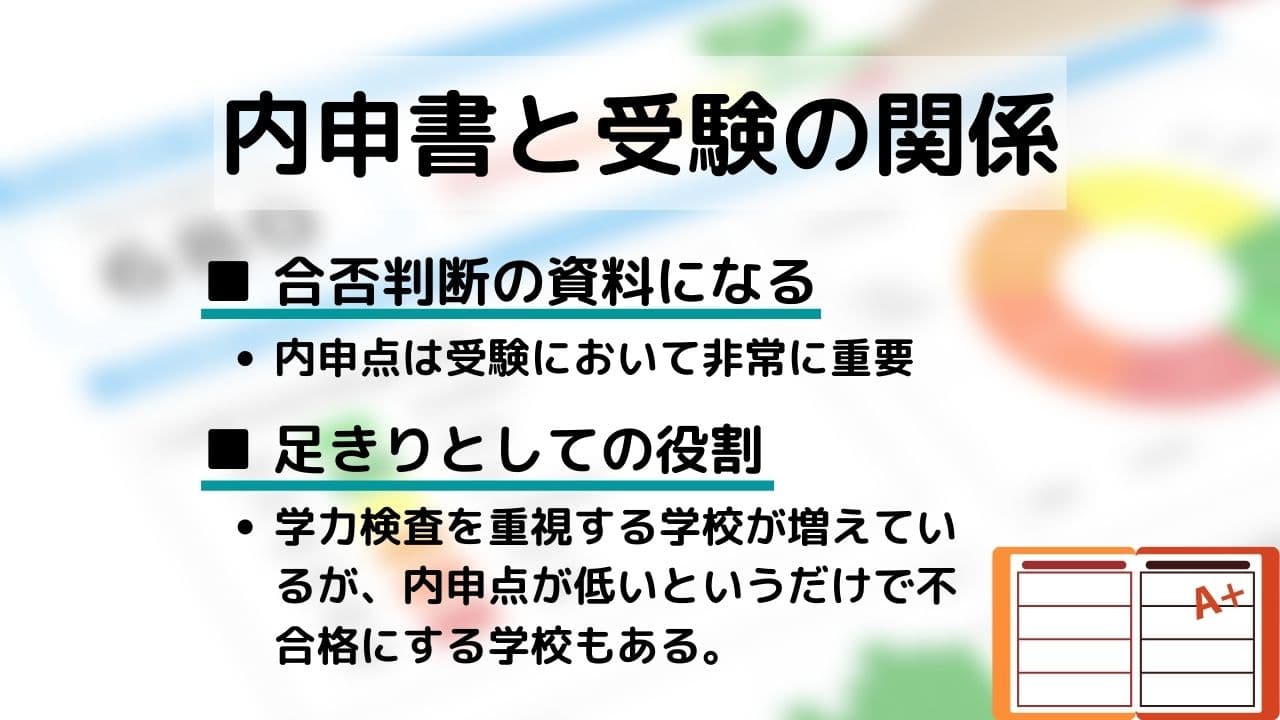
内申書は高校側が受験生を判断するために作成されるものです。
そのため、内申書が受験に与える影響は非常に大きいです。
しかし、近年の入試では学力検査を重視するという傾向があります。
これは学校側が受験生を公正に評価しやすいためです。
内申書は作成する人が学校によって、学年によってすら違います。
そのため、同じ評定5でも、中学Aと中学Bでは取り易さが全然違うということ起こりやすいです。
それでも、内申点が受験において大きな役割を果たすことには変わりありません。
内申点が低いという理由だけで不合格になる学校も存在するためです。
そのため、ボーダーラインとなる内申点はあって当然であり、それに加えて本番の試験でどれだけ取れるかが重要になります。
内申書と部活の関係
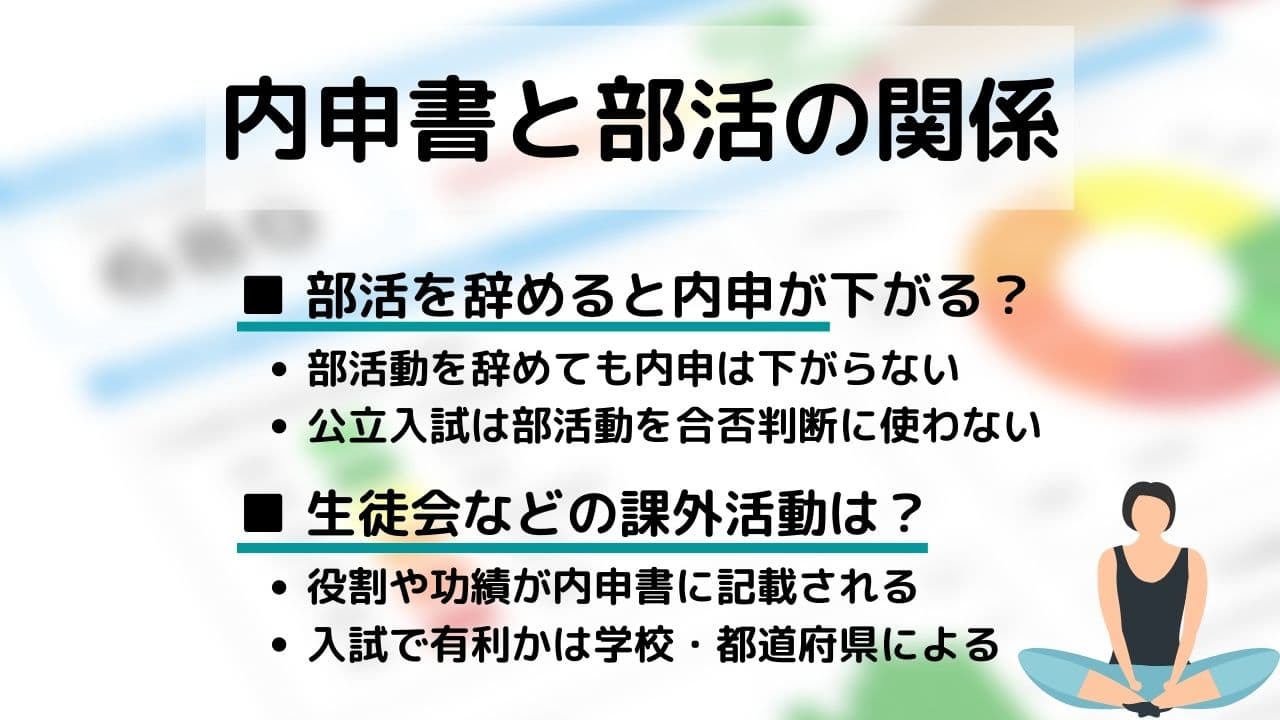
部活を辞めたり、休んだりすると内申に影響がでるのか?という質問をよくいただきます。
ここでは、部活動や生徒会活動などの課外活動がどのように内申書に影響を与えるかについて解説していきます。
部活を辞めたら/休んだら内申に影響する?
結論から言うと、部活動は内申書にほとんど影響を与えません。
内申書にネガティブな内容が書かれることはありません。
部活で優秀な成績を収めた場合は記載されますが、部活を辞めたからといって受験生にマイナスになることは書かれません。
「部活の顧問の先生なら私情が無意識に入って成績が上がるかもしれない」という意見もあります。
しかし、それが事実あるとしても考えても仕方のないことです。
部活を続けた、休まなかったからといって成績が良くなるとも断言できません
また、入試でも部活動の内容が合否判断に使われることは少ないです。
公立高校入試では全くと言っていいほど影響しません。
一部の都道府県では課外活動を点数化しているところもありますが、県大会上位入賞や全国大会レベルが評価されるレベルになります。
スポーツ推薦など、活動そのものを評価される進学方法でない限り、本人のやりたいことをするのが最適だと考えられます。
そこで実績を残せて、受験でも評価されたらラッキーくらいに考えましょう。
生徒会やその他の課外活動は?
生徒会活動をやっていた場合、内申書の規定の箇所に生徒会活動での役割が記載されます。
しかし、それが入試で有利になるかは別の問題です。
入試では、特に公立高校入試ではあまり評価対象にはなりません。
しかし、都道府県や学校により評価するところもあるのでチェックしておきましょう。
内申点を上げるために
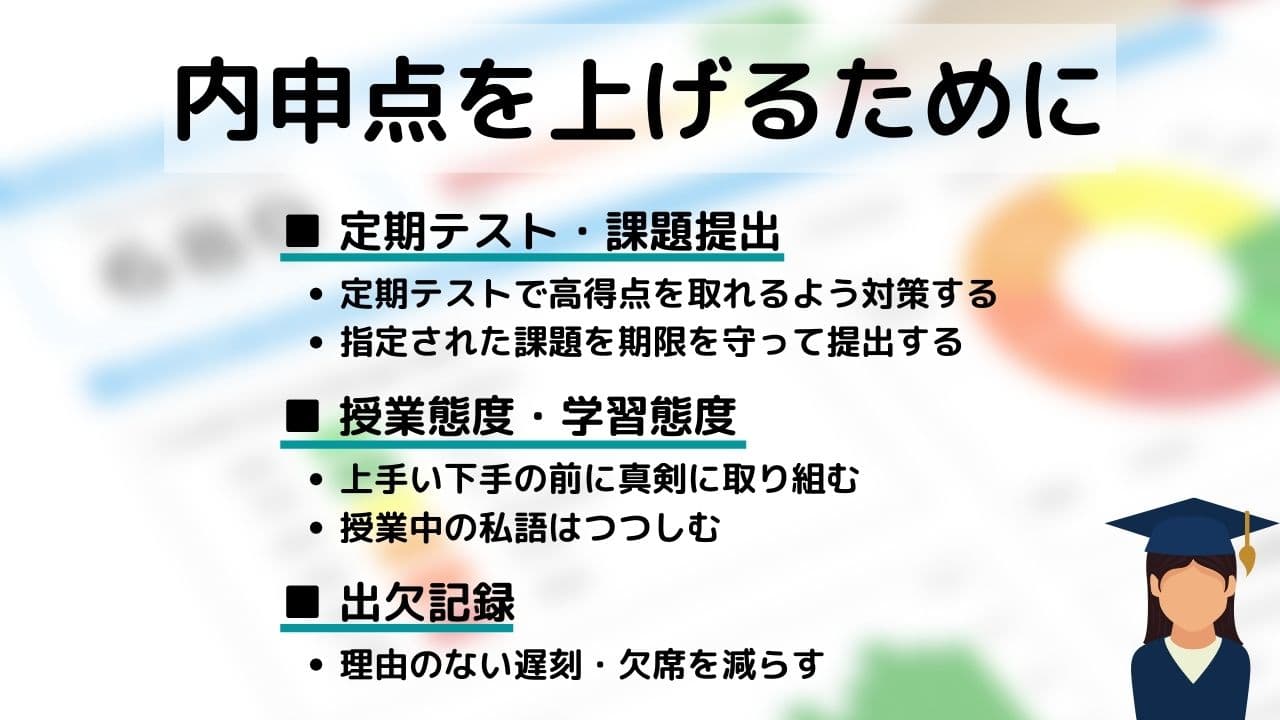
ここでは、内申点を上げるために意識すべきことを紹介していきます。
内申点を落とさないために気を付けることも同時に紹介していきます。
定期テスト・課題提出
定期テストの点数は成績をつける上で一番重要な要素となります。
学業の成績を示す一番分かり易い指標ですから当然です。
言わずもがな良い点数を取れば高い成績を取りやすくなります。
しかし、定期テストで高い点数が取れていても提出物の期限が守れていなかったり、ちゃんとやっていない場合は高い成績を取ることが出来ません。
指定された提出物は指示通りにこなしましょう。
学校の宿題をしっかり提出したいという思いはありつつも、「授業についていけておらず宿題ができない」というお子さんもいると思います。
その際にはLafの公式LINEに追加して、わからない問題の写真を送って見てください。
動画で解説してもらえるので、「わからなくて宿題ができない」という悩みを一発で解決できます。
授業態度、学習態度
点数や提出物も重要でしたが、忘れてはいけないのが授業態度・学習態度です。
出来ている/出来ていないではなく、真面目に取り組んでいるかどうかも重要な要素をなります。
テストが100点でも、先生から見て授業中の私語が気になると5をつけにくくなってしまいます。
逆に、点数は高くなくても積極的に発言している生徒には良い成績をつけやすいです。
点数は良いのに内申が低いという方は授業態度を振り返ってみましょう。
その他
内申書にネガティブなことが書かれることはないと言いました。
しかし、掲載する決まりの数字からネガティブな情報が伝わってしまうものもあります。
それは、出欠記録です。
余りにも遅刻・欠席が多いとなると、言葉でネガティブなことが書いていないくても、
良い印象を与えないことは明白です。
理由のない遅刻や欠席はなくしていきましょう。
まとめ
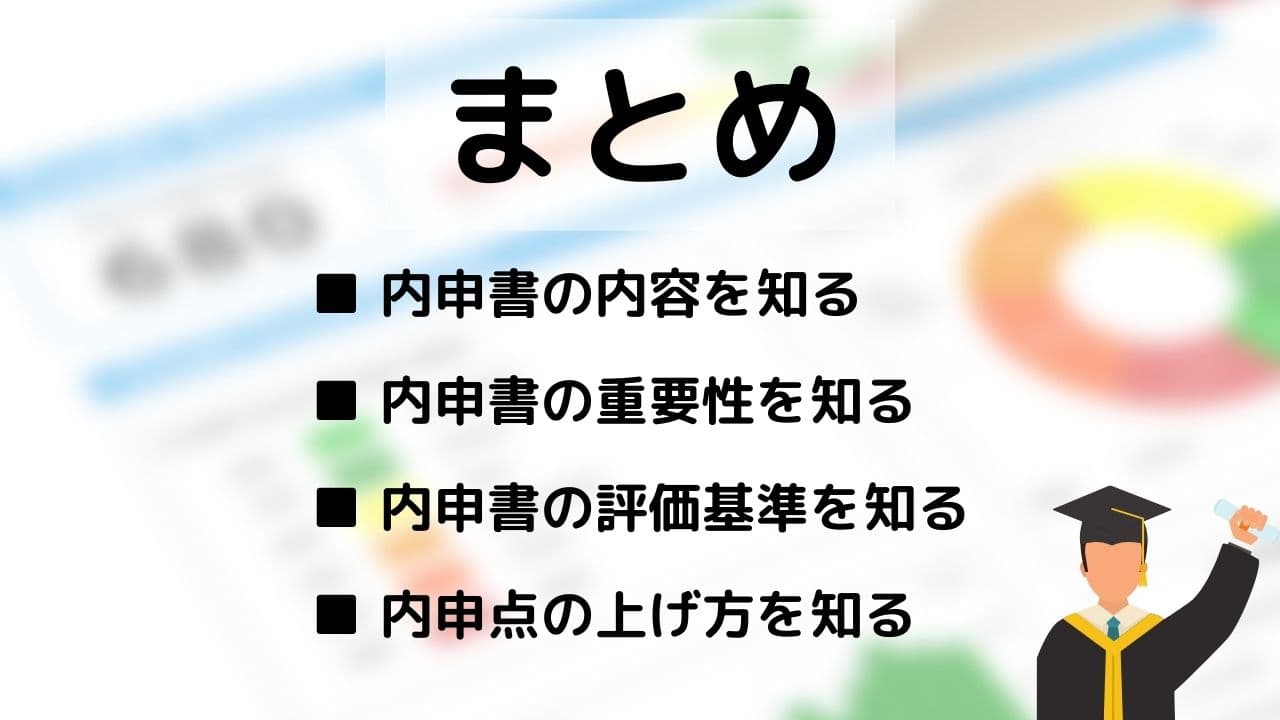
いかがでしたでしょうか?
今回は内申点とは何かから、部活と内申点の関係や注意すべきポイントも紹介しました!
受験において内申点は、その高校を受験する資格のような存在です。
内申点の仕組みを理解し、高めていきましょう!

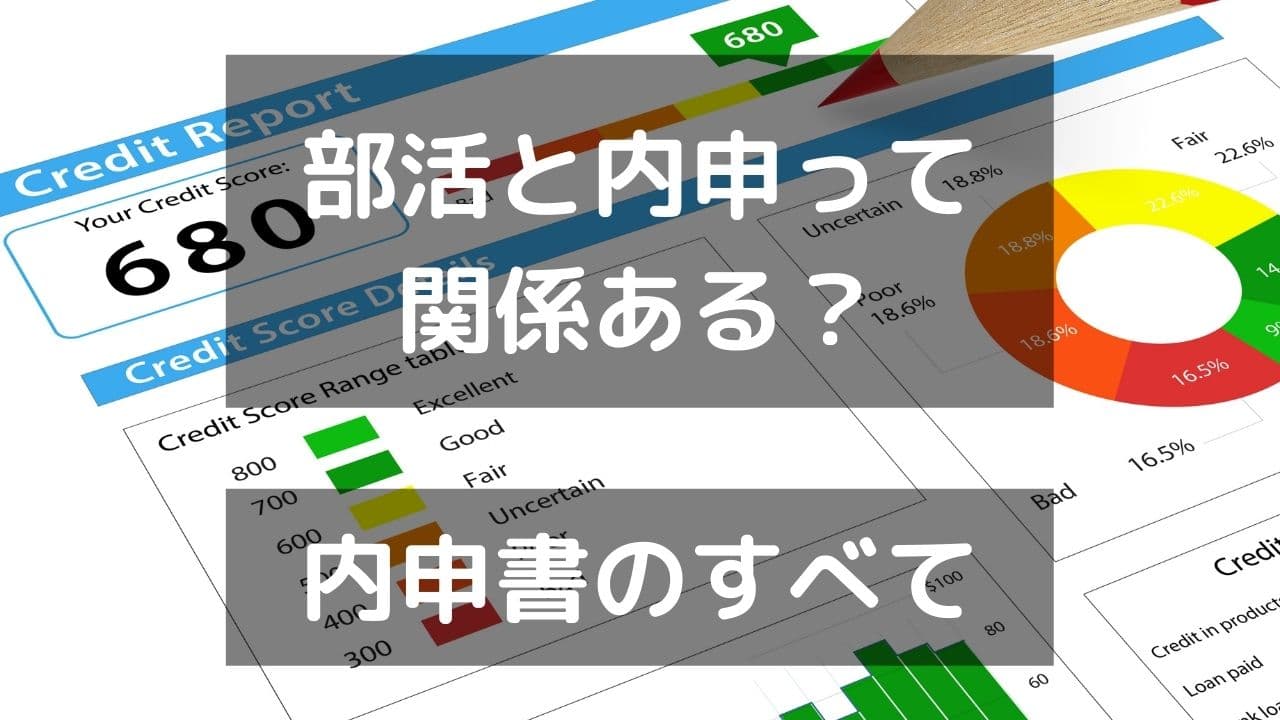


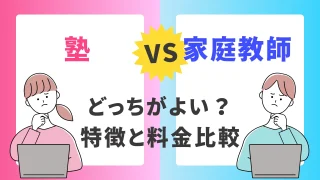
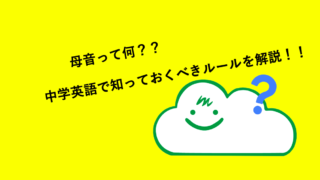


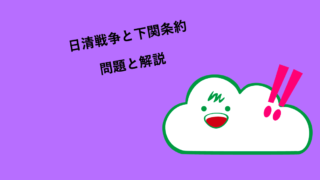
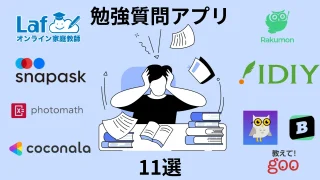

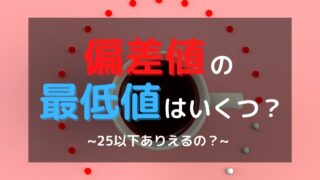
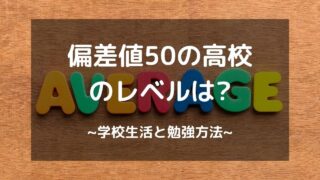
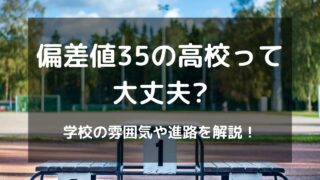

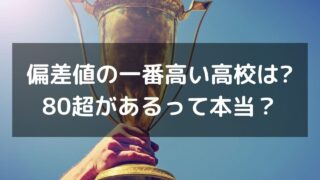
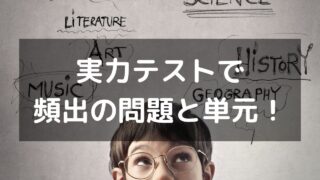
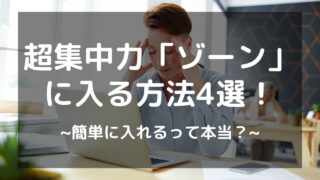
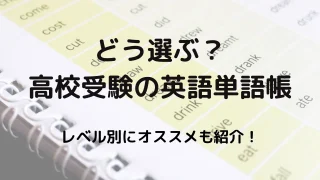

コメント一覧